
ブログBlog
気になるお悩みや最新治療について、ぜひ参考になさってください。
粉瘤とは?脂肪腫やほくろとの違いを形成外科がわかりやすく解説
皮膚の下に小さな“しこり”を見つけると、「ニキビかな」「脂肪の塊かも」「ほくろが腫れた?」と心配になります。診察してみると、その多くが粉瘤(ふんりゅう)です。ここでは粉瘤の正体と、脂肪腫・ほくろとの違い、治療の考え方をやさしく解説します。
粉瘤(表皮嚢腫)とは
粉瘤は皮膚の下に袋(嚢胞)ができ、その中に角質や皮脂がたまって少しずつ大きくなる良性腫瘍です。袋の入口は毛穴などの小さな開口部であることが多く、たまった内容物が時に外へ出ることもあります。放置して自然に治ることは基本的にありません。
原因とできやすい部位
はっきり一つの原因で説明できる病気ではありませんが、毛穴のつまり、軽い外傷や炎症後の変化、体質などが関係します。体のどこにでもできますが、顔・首・耳のうしろ・背中・胸・おしりに多く見られます。摩擦や汗が加わる部位では炎症を起こしやすく、ある日急に赤く腫れて痛むことがあります。
症状の特徴
皮膚の下にコロッとした丸いしこりが触れ、中央に黒い点(開口部)が見えることがあります。押すと白〜黄色のドロッとした内容物が出てくる場合があり、独特のにおいを伴うのが特徴です。炎症を起こすと赤く腫れ、熱感と痛み、膿を伴うことも少なくありません。
脂肪腫との違い
脂肪腫は皮下の脂肪組織が増えてできる良性腫瘍で、粉瘤のように袋の中に老廃物がたまる病気ではありません。触ったときの感触は、脂肪腫の方がやや柔らかいことが多く、皮膚表面に黒い点が見えることも通常ありません。一方、粉瘤は袋の存在が本質で、開口部が手がかりになる場合があります。ただし見た目や触診だけで完全に区別できないこともあるため、自己判断は禁物です。
ほくろとの違いと、悪性との鑑別
ほくろはメラニン色素細胞の増殖ででき、皮膚表面の色が黒〜茶色に変化します。粉瘤は皮膚色のまま、皮下のしこりとして触れる点が異なります。なかには見た目が紛らわしいケースや、まれに皮膚がんとの区別が必要な場合もあり、形がいびつ、急に大きくなる、色が不均一などのサインがあれば早めの受診が安心です。
粉瘤はうつる?悪性化する?
粉瘤は感染症ではないため、人にうつることはありません。基本的に良性腫瘍で、悪性化は非常にまれです。ただし別の腫瘍と紛らわしい例はあるため、変化が気になるときは専門医に相談してください。
治療の基本と形成外科での工夫
根本的に治すには、袋ごと取り除く摘出手術が必要です。内容物だけを出しても袋が残れば再びたまり、再発します。多くは局所麻酔での日帰り手術が可能で、小さい粉瘤なら20〜30分程度で終わることもあります。形成外科では、再発を抑える確実性と傷跡への配慮を両立させることを重視します。皮膚のしわ(皮膚割線)に沿って切開線をデザインし、嚢胞壁を破らないよう丁寧に剥離して全周を確認し、真皮内縫合と細い糸で仕上げます。顔や首など目立つ部位では特に美容面の配慮を行い、術後はテーピングや紫外線対策といったケアもご案内します。
炎症が強いときの流れ
赤く腫れて痛みが強い時期は、まず切開して膿を出し炎症を落ち着かせます。その後、状態が改善した段階で袋を確実に摘出する二段階治療の方が安全で、再発予防にも有利です。
術後の経過と再発予防
日常生活の制限は数日〜1週間ほどで、痛みは鎮痛薬でコントロール可能なことが多いです。抜糸や創部チェックのために数回の通院が必要になる場合があります。再発を避けるためには、炎症が落ち着いたタイミングで袋をきちんと取り切ること、そして術後ケアを丁寧に続けることが大切です。自己流で強く押し出す、針で刺すなどは感染や瘢痕の原因になるため避けましょう。
費用面の目安
粉瘤の手術は多くの場合で健康保険の対象です。大きさや部位、炎症の有無で手技や通院回数が変わるため、正確な費用は診察時にお伝えします。必要に応じて病理検査を行い、確定診断と類似疾患の除外を行います。
まとめ
粉瘤は皮膚の下に袋ができ、老廃物がたまる良性腫瘍で、自然には治りません。脂肪腫やほくろとは成り立ちが異なり、見た目だけでの区別は難しいこともあります。炎症や再発を繰り返す前に、早めの受診と袋ごとの摘出が安心への近道です。形成外科では、確実な摘出と傷跡への配慮を両立した治療が可能です。気になる“しこり”を感じたら、遠慮なくご相談ください。
関連記事
1. 粉瘤とは?脂肪腫・ほくろとの違いを形成外科が解説
「へそ」があるのは粉瘤かも?脂肪腫やほくろとの決定的な違いをプロが詳しく解説。
2. 皮膚のしこりは粉瘤かも?原因・症状・治療法を形成外科専門医が解説
正体不明のしこりに悩む方へ。粉瘤の典型的な症状から最新の治療法までを完全網羅。
3. 粉瘤(アテローム)のよくある質問Q&A|形成外科と皮膚科どちらで治療すべき?
脂肪腫との区別や手術の相談はどこへ?科ごとの得意分野を知って賢い病院選びを。
粉瘤治療のご案内
「そのしこり、粉瘤(アテローム)かもしれません」 当院では形成外科専門医がしこりの性質を正しく診断し、再発リスクを最小限に抑えつつ、傷跡をきれいに治すための最適な術式をご提案します。
「以前、他院で処置したけれど再発してしまった」というご相談も多くいただいております。無理な勧誘はございませんので、まずは気軽にご相談ください。
▶ ご相談・ご予約はこちらから
あわせて読みたい決定版ガイド
再発のリスクや傷跡の仕上がりに不安を感じていませんか? 数多くの症例に向き合ってきた形成外科専門医が、くりぬき法と標準摘出の違いから、術後の経過、痛み対策までを徹底解説。新潟で後悔しないための粉瘤治療のすべてを、こちらの記事に凝縮しました。
【粉瘤(ふんりゅう)治療ガイド】再発させない、きれいに治すための専門記事まとめ
クリニックからのお知らせ
当院で行っている粉瘤手術の具体的な流れや費用(保険診療)、リスクについては、ホームページの「粉瘤(アテローム)摘出手術」ページにて詳しくご確認いただけます。形成外科専門医が、再発予防と仕上がりの美しさを両立した治療をご提案します。
▶ 粉瘤(アテローム)摘出手術について詳しくはこちら(公式サイトへ)






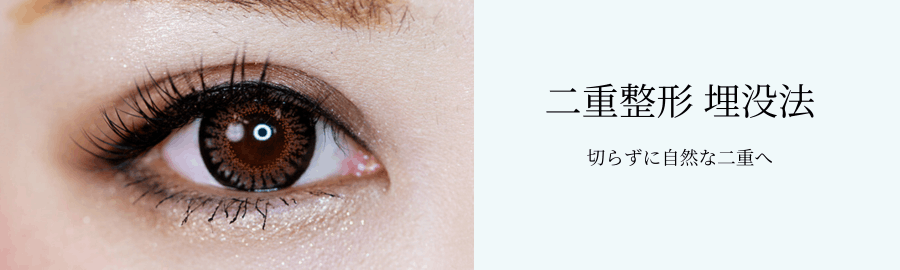



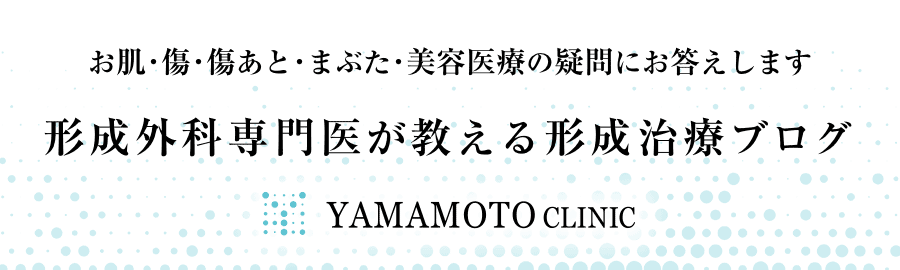

 お問い合わせ
お問い合わせ
 LINE登録
LINE登録